AIが「嘘」をつく。
こう書くとちょっと過激に聞こえるかもしれません。
でも実際、ChatGPTをはじめとする生成AIは、堂々と間違ったことを言ってくるんですよね。
私も何度も経験しました。「〇〇の定義を教えて」と聞いたら、それっぽいけど全然違う答えが返ってきたり。
そのときは「あ、やっぱりAIって万能じゃないんだ」と実感しました。
でも一方で、なぜか「かわいいな」とも思ったんです。人間も間違えるし、むしろその不完全さに親しみすら感じたというか。
とはいえ、間違いを「かわいい」で済ませられない場面はたくさんあります。
特に誤情報、著作権、依存。
この3つは私たちの生活にじわじわ影響を及ぼし始めています。
誤情報は“もっともらしい”から厄介
生成AIの一番の注意点は、誤情報です。
AIは自信満々に答えるんです。「これは絶対こうです!」みたいなトーンで。
でも、実はその根拠が曖昧だったり、完全に間違っていたりする。
私も「日本のある法律について教えて」とAIに聞いたら、存在しない条文をでっち上げられたことがあります。
最初は信じかけました。
だって文体も用語も、やたらそれっぽいんですよ。
でも調べたらまるごと嘘。あの瞬間の冷や汗は、いまだに忘れられません。
ここで怖いのは、「なんとなく正しい気がする」 という点。
人間の脳は、自分が理解できる言葉で流暢に説明されると、それだけで信じてしまう。
つまりAIは、間違っていても説得力がありすぎるんです。
だから私は、AIに答えをもらったら必ず自分で確認するようにしました。
ちょっと面倒ですが、「確認せずに信じる」リスクはもっと大きいですからね。
著作権のグレーゾーン
次に悩ましいのが著作権。
AIで画像を生成するとき、たまに「これ誰かの作品に似てない?」と不安になることがあります。
有名なアーティストのスタイルを学習しているモデルだと、そっくりな絵が出てきたりする。
一方で文章生成でも、既存の文章をほぼそのまま再現するケースがあると聞きます。
実際に私が試したときも、AIに「○○っぽい小説を書いて」と頼んだら、どこかで読んだことのあるフレーズが混じっていたんですよね。
もちろんAIは「盗用しよう」と思ってやっているわけじゃない。
ただ確率的に「それが出やすかった」というだけ。
でも法律的に見れば、「偶然」では済まされない可能性もある。
この曖昧さが今、大きな議論を呼んでいます。
私は「著作権を守ろう」という気持ちが強い方ですが、同時に「AIでしか生まれない表現の可能性」も信じています。
だから今は「完全に安心できるルールが整うまでは、公開範囲を限定する」――これを自分なりの線引きにしています。
依存という落とし穴
そして最後が依存です。
AIは便利すぎるんです。
調べ物も、文章作成も、アイデア出しも。とにかく一瞬で助けてくれる。
だからこそ、気づかないうちに「自分で考える力」を削がれてしまう危険があるんですよね。
私も一度、「今日の夕飯何作ろう」とAIに相談してから数週間、ずっとAI任せになっていたことがあります。
その結果、買い物も献立もマンネリ化。なんだか「自分で決める」感覚が薄れて、ちょっと怖くなりました。
それ以来、「AIはアイデアを広げる相棒、でも最終決定は自分」というルールを決めました。
これだけでも依存の度合いがかなり減ったんです。
AIはあくまで道具。主役はあくまで自分。
この意識を持っているかどうかで、AIとの付き合い方は大きく変わると思います。
余談:AIを疑うのは、結局「人間を疑う力」でもある
ここでちょっと脱線します。
AIが嘘をつくことに慣れてくると、逆に「人間の発言」にも慎重になるようになったんです。
SNSで流れてきた情報に対して、「本当にそう?」と立ち止まるクセがついた。
つまりAIと付き合うことは、結果的に「情報を疑う力」を鍛えているとも言えるんですよね。
皮肉だけど、これって意外とポジティブな副作用かもしれません。
まとめ
生成AIの注意点は、
-
誤情報にだまされやすい
-
著作権のリスクがある
-
便利すぎて依存する危険がある
この3つが大きな柱です。
でも、ただ怖がる必要はありません。
誤情報は「必ず確認する」、著作権は「公開範囲を工夫する」、依存は「自分で決める意識を持つ」。
この3つを意識するだけで、AIとの付き合い方はぐっと健全になります。
AIは嘘をつく。だけど、それを前提にすれば、むしろ頼れる相棒にもなる。
そう思うと、「AIと一緒に生きていく未来」も悪くないな、と私は感じています。
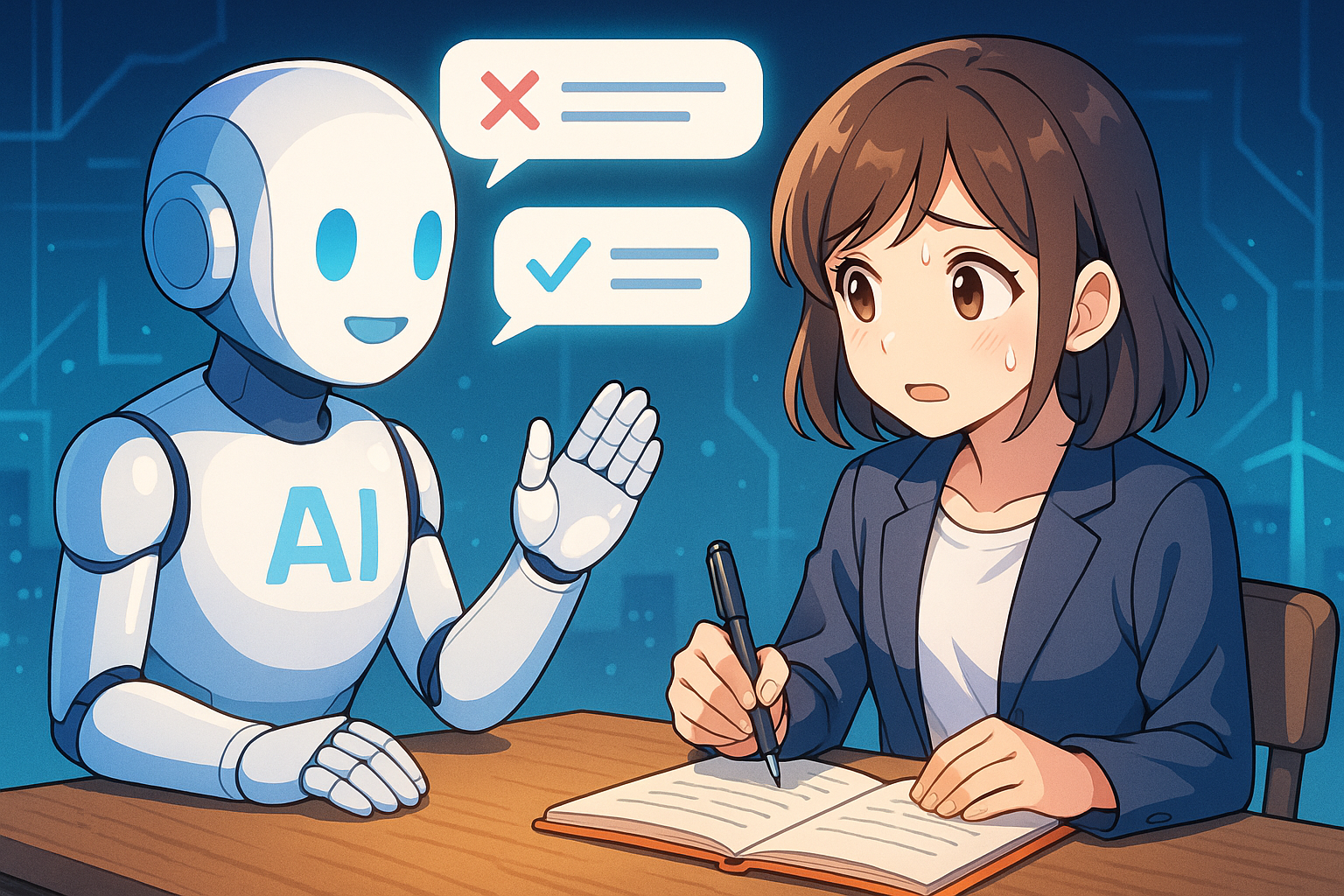


コメント