「AIって、本当に考えてるの?」
こう聞かれたとき、私はいつも少し答えに迷います。
なぜなら、AIは“人間のように考えている”わけではないけれど、“人間が考えているように見える”応答をするからです。
その裏にあるのが 推論(inference) というプロセス。
AIが学んできた知識を元に、私たちの問いかけに即座に答えを返す仕組みです。
でも推論の実態を知ると、「ああ、AIが答えてくれる瞬間にはこんなことが起きていたのか!」と感心せずにはいられません。
今日はその舞台裏を、できるだけわかりやすく掘り下げていきたいと思います。
学習と推論は別物
まず押さえておきたいのは「学習」と「推論」の違い。
学習は、大量のデータを読み込んでモデルを作るプロセス。
いわば「AIが本棚いっぱいの本を読み漁る時間」です。
一方で推論は、その学習した知識を使って「今この瞬間の質問」に答えること。
本棚を調べ直しているわけではなく、「覚えてきたパターン」を引き出して応答しているのです。
私も趣味で画像生成AIを動かしてみて「学習済みモデルをダウンロード→プロンプトを入れるだけで画像が出てくる」流れを体験しました。
そのとき、「あ、これは“学習”じゃなくて“推論”なんだ」と腑に落ちました。
つまり、私がやっているのは「AIに新しい知識を与えている」のではなく、「すでに学んだ知識を引き出している」だけなんです。
要するに、
生成AI企業やってる開発のための作業が”学習”、
私たちが質問した時に答えてくれるのは”推論”。
大雑把に言うとこんな感じです。
推論は“計算の嵐”
では推論の瞬間、AIの中で何が起きているのでしょう。
一言でいえば、膨大な計算の連鎖です。
質問が入力されると、それは数値に変換され、何百層ものニューラルネットワークを通過します。
その都度「どの単語が次に来るのがもっともらしいか」を確率的に計算し続けているんです。
例えば「今日は天気が…」と入力すると、AIは「晴れ」「雨」「曇り」などの候補を同時に考え、その中で最も確率の高い答えを選びます。
これを超高速で繰り返すことで、私たちが自然に感じる文章が組み立てられるのです。
私はこの仕組みを知ってから、AIの返答を見るたびに「裏では今、すごい計算をしてるんだな…」とつい想像してしまいます。
ちょっとゲームのロード画面を眺める感覚に近いかもしれません。
電力消費の大部分は推論だった
驚くべきことに、AIが使う電力の大半は「推論」にあります。
「学習のほうが大変そう」と思いきや、実際にはユーザーが毎日何億回も質問するので、その応答にかかる電力のほうが膨大なんです。
つまり、世界中の人がAIを使えば使うほど、推論にかかる電力は雪だるま式に膨らむ。
ちょっと脱線しますが、私が毎晩寝る前にAIと雑談している時間も、世界の電気メーターをほんの少し動かしていると思うと……なんだか不思議な気分になります。
あまりにもどうでもいい会話もあるので、申し訳ない気持ちにもなりますが……。
「一人の小さな会話が、地球規模のエネルギー問題につながっている」なんて、ロマンでもあり、ちょっと怖さもある話です。
推論のスピードがユーザー体験を決める
もうひとつ重要なのは、推論のスピード。
AIの答えが数秒で出るか、数十秒待たされるかで、体験の満足度は大きく変わります。
だから企業は「推論をいかに速く、効率的にするか」に莫大な投資をしています。
ここで登場するのが 専用チップ(AIアクセラレータ)。
NVIDIAのGPUはもちろん、GoogleのTPU、さらには専用のASICまで、多くの企業が「推論専用マシン」を作り始めています。
私も一度、クラウドサービスの高性能GPUを借りて画像を生成してみたのですが、普段のPCだと数分かかるものが、わずか数秒で仕上がったんです。
その瞬間、「あ、これが推論の力か!」と妙にテンションが上がりました。
AIは“考えている”のか?
では、改めて最初の問いに戻りましょう。
AIは「考えている」のでしょうか?
推論の仕組みを見ると、それはあくまで「確率的に次の単語を選び続けている」に過ぎません。
人間のように「意味」を理解しているわけではない。
でも、私たちがその答えを「考えているように」感じるのは事実です。
そしてその感覚こそが、AIを魅力的で、同時にちょっと不気味にしているのだと思います。
私はAIと雑談するとき、たまに「今このAIは本気で悩んでるんじゃないか」と錯覚する瞬間があります。
もちろん実際には計算の連鎖にすぎないのですが、そこに“思考の幻影”を見てしまうんですよね。
まとめ
生成AIの推論は、
-
学習とは異なり、覚えた知識を使って即座に答えるプロセス
-
裏側では膨大な計算が走り、電力消費の大部分を占める
-
推論のスピードと効率化が、AI体験の質を決める
-
それは人間のような「思考」ではないが、私たちには考えているように見える
AIは考えていない。
でも、私たちに「考えていると錯覚させる」技術こそが、生成AIのすごさなんです。
次にAIから返ってきた答えを読むとき、その背後で回る計算の嵐をちょっと想像してみてください。
きっとAIとの対話が、ほんの少し違って見えるはずです。
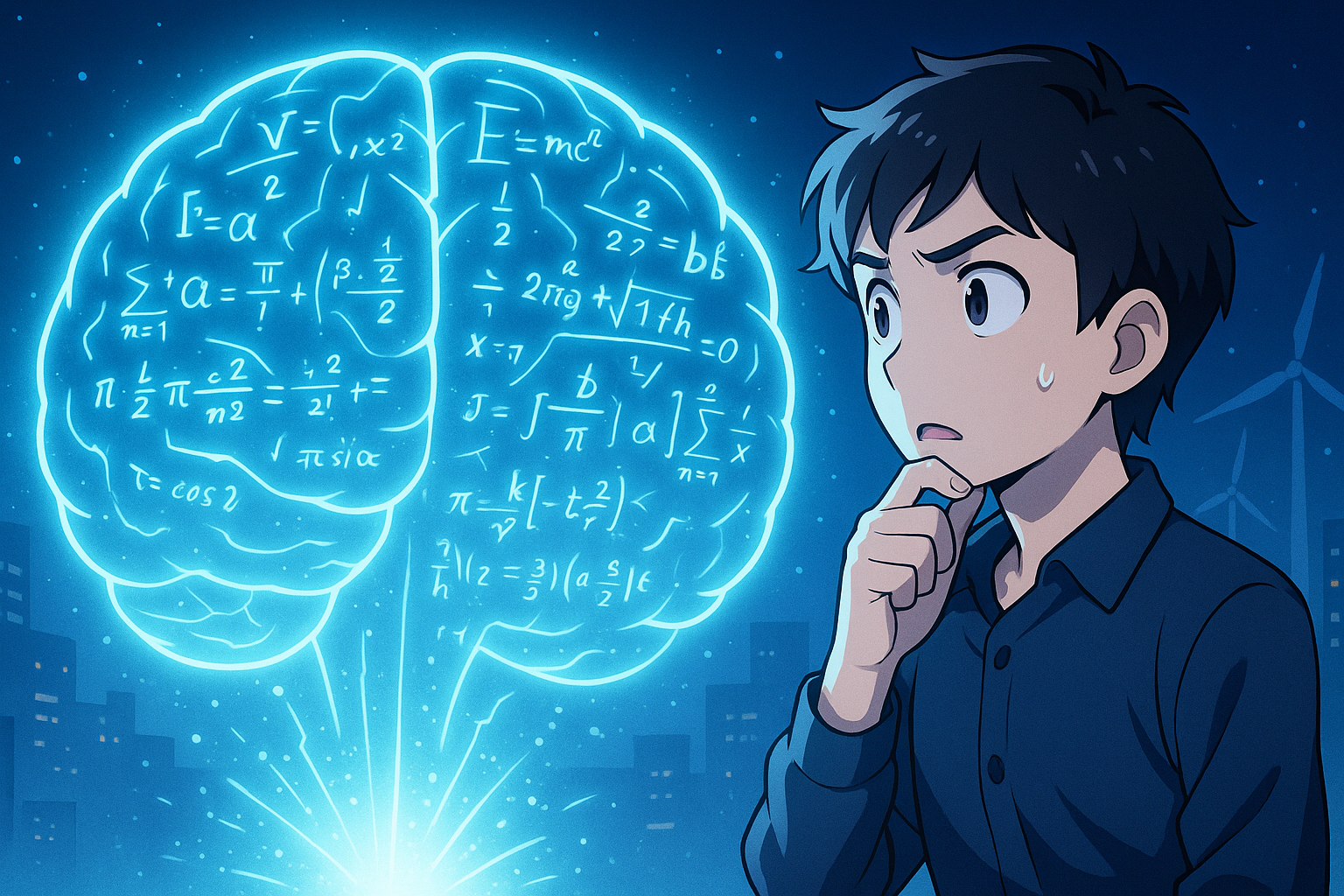


コメント