「AIって別にテキスト生成してるだけだから電気はそんなに使わないでしょ?」
そう思っていたのですが、調べてみて驚きました。
昨日の半導体の話の時も少しお話ししましたが、生成AIはむしろ“電気を食う怪物”だったんです。
ChatGPTに一回質問するたびに、裏側では大量のGPUがフル稼働。
その結果、消費電力は驚くほど膨らんでいます。
AIの未来を考えるとき、私たちは「頭脳の進化」だけでなく「電源コードの限界」とも向き合わなければなりません。
生成AIはなぜこんなに電気を食うのか
生成AIの学習や推論は、とにかく計算量が桁違い。
例えばGPT-4のような巨大モデルは、数千億のパラメータを扱います。
これを動かすには何千枚ものGPUが必要で、それぞれが一斉に電力を消費するのです。
私も趣味で画像生成AIを触っていて「GPUのファンが唸り始める瞬間」を体感しました。
家のPCですら電気メーターが上がっているのが分かるレベル。
これをデータセンター規模でやったら、そりゃあ電力を爆食いするのは当然ですよね。
世界規模での影響
研究者の試算によると、生成AIの電力消費は今後 中規模国家一国分の年間消費量 に匹敵する可能性があるそうです。
つまり、「あなたがChatGPTに質問する=どこかの発電所が少しだけ頑張っている」という構図。
ちょっと笑い話みたいですが、積み重なれば笑えない規模です。
もしAI利用がさらに拡大すれば、電力網や発電システムへの負荷は避けられません。
「AIを動かすために停電が増える」なんて未来、想像したくないですよね。
持続可能性への挑戦
では、このまま暴走してしまうのか?
答えは「工夫次第で変えられる」です。
大手IT企業はすでに 再生可能エネルギー を取り入れ始めています。
GoogleやMicrosoftは、データセンターを太陽光や風力で動かす取り組みを加速中。
さらに、「より省エネな半導体」を開発することで、一度の処理に必要な電力を減らそうとしています。
私も省エネを意識して、自宅ではGPUを回す時間を夜間にずらすようにしています。
電力料金も少し安いし、なんとなく「地球に優しいことをしてる」気分になれるんですよね(笑)。
デメリットは、寝るときちょっとファンの音がうるさいことですかね(笑)。
こういう小さな工夫の積み重ねが、大規模なAI利用でも必要になるのかもしれません。
それでも避けられない課題
とはいえ、省エネや再エネで全て解決できるわけではありません。
-
電力インフラ:発電はできても送電網が追いつかない
-
地域格差:都市部の需要増に対し、地方の供給は過剰になることも
-
コスト:再エネや新半導体はまだ高く、大量導入には壁がある
つまり、「技術の進化」と「社会の仕組み作り」が同時に必要なんです。
ちょっと脱線しますが、私は昔「電気はいつでもただで好きなだけ使える」と信じていました。
でも始めて電気代の明細を見た瞬間、「電気って意外と高いんだな」と驚いたものです。
今のAIブームも、それと同じ段階に来ているのかもしれません。
未来に向けて私たちができること
ここまで読むと「AIを使うのは環境に悪いの?」と落ち込む人もいるかもしれません。
でも私は逆にワクワクしているんです。
なぜなら、AIの電力問題は 「使い方を工夫すれば改善できる余地が大きい」 から。
たとえば、
-
無駄に同じ質問を繰り返さない
-
軽量なモデルをうまく活用する
-
企業や開発者に省エネ技術の導入を求める
こうした小さなアクションでも確実に意味があります。
そして何より、「電気をどう使うか」を考えることは、自分たちの未来の暮らしを考えることにつながります。
「AIを動かす電気は、どこから来ているんだろう?」
そう問いかけるだけで、私たちは新しい学びと気づきを得られるはずです。
まとめ
生成AIは今、その頭脳とともに、消費電気も爆発的に伸ばしています。
-
AI利用が進めば、中規模国家レベルの電力を必要とする
-
再生可能エネルギーや省エネ半導体が解決策として期待されている
-
しかし、送電網やコストなどの課題もまだ大きい
-
小さな工夫や意識の変化が、未来を持続可能にする第一歩になる
持続可能か、それとも暴走か。
その未来は、AIを使う私たち一人ひとりの選択にもかかっています。
次にChatGPTを開いたとき、少しだけ「裏で回る電気メーター」を想像してみませんか?
きっとAIとの付き合い方が、ちょっと違って見えるはずです。

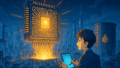
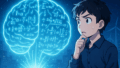
コメント