「生成AIを学びたいけど、どこから始めればいいんだろう?」
これは、私が最近よく相談される質問です。
ChatGPTやStable Diffusionのようなツールが一気に広まり、「とにかく触ってみたい!」という人から、「仕事に本格的に活用したい」という人まで、学びたい層はぐんと広がりました。
ただ、独学だけでは限界があります。
そこで役立つのが 勉強会やオンライン講座 です。
今日は「どんな学びの場を選ぶべきか」を、実体験や小話を交えながらご紹介します。
なぜ勉強会なのか?
生成AIはとにかく変化が速い分野です。
昨日の最新情報が、今日にはもう古くなっている。
独学で情報を追い続けるのはかなり大変なんですが、勉強会や講座なら「要点がまとまっている」上に「仲間ができる」というメリットがあります。
私も最初はYouTubeや書籍で学んでいたのですが、ある日ふと「これ、本当に最新なのかな?」と不安になったんです。
そんなときに参加したのが、とある生成AIの勉強会。
そこで講師が「このAPIは来月終了予定です」とサラッと言ったんですよ。
……書籍ではまだ「便利なAPI」として紹介されていたのに!
この体験から「やっぱり現場の人と学ぶことが大事だな」と実感しました。
オフライン勉強会の魅力
まずはオフラインの勉強会について。
東京や大阪など都市部では、毎週のようにAI関連の勉強会が開催されています。
内容は「初心者向けのハンズオン」から「企業の事例紹介」まで幅広い。
オフラインの良さは、やっぱり「人とのつながり」です。
休憩時間に隣の人と話すだけで「そんな使い方があるんだ!」と学べることが多いんです。
実際に私が参加したある勉強会では、デザイナーさんが「Stable Diffusionでラフを描いて、クライアントとの合意形成を早めている」と話していました。
私はてっきりAIはエンジニアが中心に使っているものだと思っていたので、目から鱗でしたね。
ただしデメリットもあって、地方だと開催数が少ないのが現実。
「行きたいけど遠い」という人は多いでしょう。
オンライン講座という選択肢
そこで役立つのがオンライン講座です。
UdemyやSchoo、YouTubeの有料講座まで、選択肢は無数にあります。
メリットは「自分のペースで学べること」と「場所を問わないこと」。
私もオンライン講座でPyTorchの基礎を学びました。
夜中に眠れなくて布団の中で講義を聞きながらノートを取ったこともあります。
(正直、寝落ちして講義が頭に入らなかったこともありますが……笑)
最近では生成AI特化のオンラインコミュニティも増えていて、SlackやDiscordで質問できる場がセットになっているものも。
「一人じゃ続かない」という人には特におすすめです。
初心者が選ぶべき勉強会・講座
では初心者はどんな場を選べばいいのでしょうか。
私のおすすめは、まずは 「体験型」の勉強会や講座 です。
例えば「プロンプトエンジニアリング入門」や「画像生成AIハンズオン」。
手を動かしながら学べるので、「わかった気になる」だけで終わらないのが大きなメリットです。
また、初心者向け勉強会は雰囲気が柔らかいのもいいところ。
私も最初に参加したとき、分からないことだらけで不安でしたが、講師が「ここでつまずくのは普通です」と言ってくれてホッとした覚えがあります。
とにかく「まずは触ってみる」ことが第一歩。
中級者・プロ向けの学び
一方、ある程度使い慣れてきたら「事例共有型」の勉強会が役立ちます。
たとえば「生成AIを使ったマーケティング成功事例」とか「業務システムへのAI統合」など。
ここでは実際に試してみた企業の生の声が聞けるのが大きいです。
私は以前、AIカスタマーサポートを導入した企業の発表を聞いたのですが、裏側の「失敗談」がとても参考になりました。
表向きはスムーズにいったように見えても、実際は「誤回答が多発してクレーム対応に追われた時期があった」と。
こうしたリアルな話は、ネット記事だけではなかなか出てきません。
プロを目指すなら、論文読み会やKaggle勉強会といった「研究寄り」の場に飛び込むのも良いですね。
正直ハードルは高いですが、参加してみると「ここでしか得られない知見」があります。
勉強会で得られる「仲間」という財産
最後に、勉強会の最大の価値は「仲間と出会えること」だと思います。
AIは一人で学べなくもないですが、正直孤独です。
エラーが出たとき、相談できる相手がいるかどうかで学習スピードは全然違う。
私は勉強会で知り合った仲間と、いまでも定期的にオンラインで情報交換をしています。
「このプラグインが便利だったよ」とか「こんな失敗をした」とか。
そうしたやり取りが、継続的な学びのモチベーションになるんです。
だからこそ、「生成AIを学びたい」と思ったら、まずは勉強会や講座をのぞいてみてほしい。
そこから新しい出会いと発見が広がるはずです。
まとめ
生成AIの学び方は人それぞれですが、
-
最新情報を得たいなら勉強会
-
自分のペースで学ぶならオンライン講座
-
初心者は体験型、中級者以上は事例共有や研究寄りへ
この流れを意識すれば、迷うことはありません。
独学だけでは届かない「リアルな知識」や「仲間」との出会いが、勉強会にはあります。
生成AIはまだまだ広がる分野。
一人で抱え込まず、ぜひ仲間と一緒に学び、未来を切り拓いていきましょう。
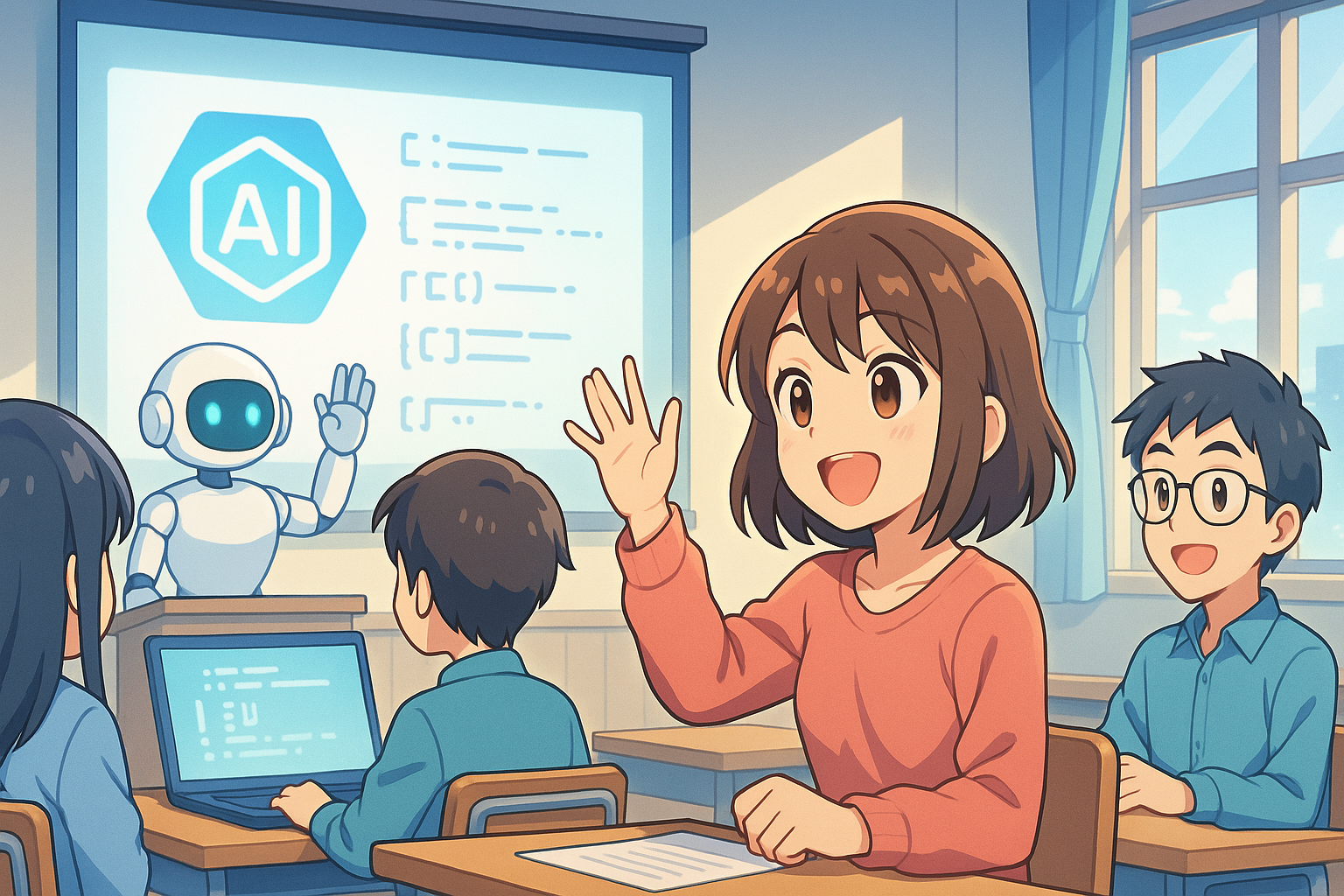
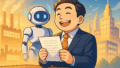

コメント