AIの技術革新が日常にまで浸透しつつある今、システム開発やサービス設計における「要件定義」の重要性はこれまで以上に高まっています。
しかし、生成AIを活用したプロジェクトは従来の手法とは違い、正解が曖昧で、変化も早い。だからこそ「何をどう決めればいいのか」で多くの人が悩んでいるのではないでしょうか。
私自身、過去にAI関連の企画に携わったとき、要件定義の難しさに直面しました。完成形がイメージしづらく、関係者ごとに理想も違う。議論がすれ違うたびに不安になり、夜中に「このままで本当に形になるのだろうか」と悩んだものです。
そんな経験を経てわかったのは、生成AI時代の要件定義には新しい発想とアプローチが必要だということです。
この記事では、そのポイントを整理しながら、あなたに「できるかもしれない」という勇気を届けたいと思います。
変化する要件定義の役割——曖昧さを受け入れる姿勢がカギ
従来のシステム開発では、要件定義は「完成品の設計図」を描くようなものでした。必要な機能、処理の流れ、利用者の動き——すべてを最初に決め込むのが当たり前だったのです。
しかし生成AIを活用する場合、その前提は大きく揺らぎます。なぜなら、AIの出力は完全にコントロールできるものではなく、ユーザーとのやりとりの中で柔軟に変化するからです。
私があるチャットボット開発に参加したときも、「ユーザーがどう質問するか」によって結果がまったく変わり、最初に作った設計図はほとんど役に立ちませんでした。
そのとき痛感したのは、要件定義とは「決める」ことではなく「変化に備える」ことなのだということです。
AI時代の要件定義は、完成形を固定する作業ではなく、進化を受け止める「器」を用意すること。
曖昧さを恐れるのではなく、むしろ前提として受け入れる柔軟さが必要なのです。
ステークホルダーとの対話——共感を育むプロセスこそ最重要
AIプロジェクトが失敗する最大の原因は「関係者の認識のズレ」です。
特に生成AIは、使う人によって体験が変わるため、想像しているゴールが人ごとに異なるケースが多発します。
私が忘れられないのは、ある企業での導入プロジェクト。経営者は「業務を効率化したい」と語り、現場の社員は「仕事を奪われるのでは」と不安を抱えていました。
同じAI導入でも、見ている景色がまったく違ったのです。
そのとき私たちが取ったのは、まず「みんなでAIを実際に触ってみる」ことでした。机上の議論だけではなく、体験を共有することで初めて「なるほど、こういう便利さがあるのか」と認識が揃っていったのです。
要件定義の核心は、仕様を文書に落とし込むことではありません。
関係者の心の距離を縮め、共感を育むこと。これを忘れてはいけないと強く思います。
ユースケースの明確化——「誰がどう使うか」に焦点を当てる
AIの要件定義で最も大事なのは、「どの技術を使うか」よりも「誰がどう使うか」を描くことです。
たとえば同じ文章生成AIでも、マーケティング部門が使う場合は広告コピーの作成が目的になりますし、カスタマーサポート部門なら問い合わせ対応が中心になります。
このようにユースケースを明確にしないまま技術の議論をしても、空回りしてしまうのです。
私が関わったある案件では、最初に「最新のAIモデルを導入する」ことばかりに意識が向き、実際に誰がどんな場面で使うのかが抜け落ちていました。結果として、せっかくの投資が十分に活かされず、現場には「やっぱり使いにくい」という声があふれてしまいました。
そこで学んだのは、要件定義は“利用者の物語”を描く作業だということです。
どんな場面で、どんな感情で、どんな結果を期待してAIを使うのか。
それを具体的に描き出すことで、自然と必要な機能や仕様が見えてきます。
プロトタイピングの重要性——「完璧」より「早く試す」
生成AIを活用した開発では、完璧を目指すより「まず試す」ことが圧倒的に大事です。
なぜならAIの振る舞いは事前にすべてを想定できないからです。
私もかつて「しっかり計画してから」と構えていた時期がありました。
しかし、いざ使ってみると想定外の挙動ばかり。
そのたびに資料を修正し、会議をやり直し……結局、膨大な時間を無駄にしてしまったのです。
そこから学んだのは、AI開発は「走りながら考える」方がうまくいくということでした。
小さな試作品(プロトタイプ)を早く作り、実際に触りながら改善を重ねる。
これが生成AI時代の要件定義を成功させる近道なのです。
継続的改善——要件定義は「終わらない旅」
従来のプロジェクトでは、要件定義は最初に一度だけ行い、その後は基本的に固定されるものでした。
しかしAIを活用するプロジェクトでは、その考え方は通用しません。
AIモデル自体がアップデートを繰り返し、利用者の期待も日々変化していきます。
だからこそ、要件定義は「一度決めて終わり」ではなく「常に見直し続ける」営みでなければならないのです。
私はある導入案件で、半年ごとに「要件定義を再定義するワークショップ」を実施しました。
最初は「そんなに頻繁にやる必要があるのか」と懐疑的だったメンバーも、実際にやってみると「現場の変化を反映できるのはありがたい」と前向きに変わっていきました。
要件定義とは、未来に向けて組織が「進化を続ける覚悟」を形にする作業なのです。
あなたに伝えたいこと——不安を越えて挑戦する勇気
生成AIのプロジェクトに関わると、きっと不安や戸惑いに直面するでしょう。
「どこまでAIに任せていいのか」
「この決定は正しいのか」
「失敗したらどうしよう」
私も同じでした。何度も自信をなくし、迷いました。
でも、試行錯誤を重ねて気づいたのは、不安を感じるのは挑戦している証拠だということです。
要件定義は未来を決める作業ではありません。
未来を一緒に探し続けるための出発点なのです。
だから、完璧を求めすぎず、一歩を踏み出してください。
その小さな一歩が、AIと共に歩む大きな未来を開いていきます。
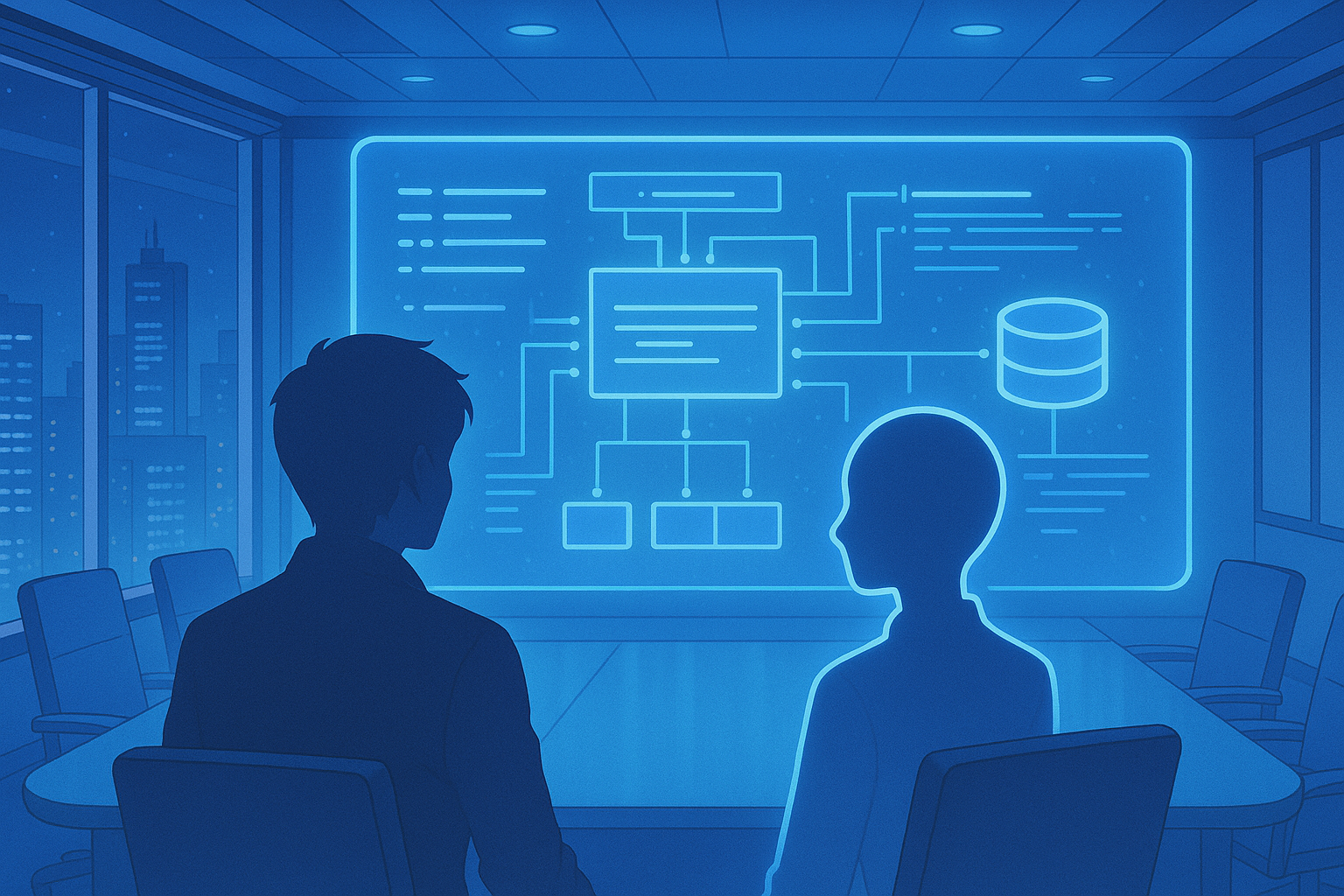


コメント