「生成AIって、作れるの?」
そう聞かれたら、私は迷わず「作れる!」と答えます。
もちろんGoogleやOpenAIみたいな巨大モデルを個人で作るのは現実的じゃありません。
でも、小さなスケールで「自分専用AI」を育てることは、思っているよりずっと身近なんです。
実際に私は趣味で、文章生成や画像生成の簡易モデルをいじってみました。
その過程はワクワクと苦労の連続でしたが、「あ、自分でもできるんだ」という感覚は本当にやる気を上げてくれます。
今回は、そんな 生成AI自作プロジェクトの始め方と、避けられない落とし穴 をまとめてみました。
まずは「ファインチューニング」から始めよう
いきなりゼロからモデルを学習させるのは無謀です。
必要なデータも計算資源も桁違い。電気代だけで数百万円なんて話もあります。
そこで現実的なのは ファインチューニング。
すでに学習済みの大規模モデルをベースに、自分のデータを追加して調整する方法です。
たとえば「小説風の文章をもっと得意にしたい」と思ったら、自分が書いた小説や好きな作家の文体をデータとして学習させる。
すると、元のモデルにちょっとした「味付け」が加わり、自分専用AIっぽくなるんです。
私もブログ記事用に「カジュアルで共感を呼ぶ口調」をAIに覚えさせようと試したことがあります。
少量のデータでも思った以上に性格が変わってくれて、「おお、こっちの方が親しみやすい!」と感動しました。
必要なのはGPU?クラウド?
自作AIのハードルのひとつが 計算環境。
ローカルPCで動かすなら、高性能GPUが必要です。
でも私のような「普通の会社員+趣味でAIをいじってる人間」にとって、何十万円もするGPUをポンと買うのは現実的じゃありません。
そこで頼りになるのが クラウドサービス。
Google ColabやKaggle、あるいは有料クラウドGPUレンタルを使えば、数百円〜数千円単位でハイパワーな環境を使えます。
私も最初はColabで始めました。
「GPUを起動する」ボタンを押すだけで、ローカル環境では数時間かかる処理が数分で終わる。
これを体験した瞬間、「これなら普通のPCでも全然いける!」とテンションが爆上がりしました。
データ集めの楽しさと難しさ
AIを自作するうえで、実は一番大変なのが データ集め です。
大量の高品質データがあればあるほどAIは賢くなります。
でも、著作権やプライバシーの問題もあるので「拾ってきたものを何でも学習させればいい」というわけにはいきません。
私は趣味で「旅行ブログ用のAI」を作ろうとして、自分が書いた日記や撮った写真をデータにしました。
集めている途中で「なんだか宝箱を整理してるみたいだな」と楽しくなった反面、「あ、こういうデータはAIに向かないのか」と気づかされることも多かったです。
つまり、AIを作る過程は「自分のデータと本気で向き合う時間」でもあるんですよね。
落とし穴① 思った通りには動かない
最初にぶつかる壁は、「学習させても期待通りの結果が出ない」ということ。
たとえば猫の画像を学習させたのに、生成された画像は耳の形がおかしかったり、毛並みが妙にのっぺりしていたり……。
「え、なんでこうなるの?」と首をかしげる瞬間が必ず訪れます。
私も文章生成AIを調整したときに、「共感を強調してほしい」と思ったら、逆にやたらと「わかりますよね!」ばかり連呼するAIができあがってしまいました(笑)。
思い通りにいかないのも、ある意味では“育ててる感覚”があって面白いんですけどね。
落とし穴② 電気代と時間の罠
もうひとつの落とし穴は、電気代と時間。
小規模なモデルでも、何時間もGPUを回し続けると、電気代は意外とかさみます。
「AIを育てたい!」という熱意で夜中まで回していたら、翌月の電気代明細を見て青ざめた……なんて経験をした人も多いはず。
私はそこで「学習はクラウドに任せて、推論だけローカルで」という使い分けに落ち着きました。
これなら電気代も節約できるし、時間のロスも少なくなります。
落とし穴③ 飽きる瞬間
正直に言うと、途中で「飽きる瞬間」もやってきます。
最初はワクワクして始めたのに、学習が終わるまで待つ時間や、エラーで立ち止まる瞬間に「なんで俺こんなことしてるんだろう」と思うことも。
でも、そこで踏ん張ってちょっと工夫すると、またAIが面白い反応を返してきて一気にテンションが戻るんです。
これはまるで、難しいゲームのボス戦で苦戦して、やっと勝てたときの爽快感に近い。
「落とし穴と達成感のジェットコースター」――これが自作AIの醍醐味なのかもしれません。
まとめ:AIをDIYする喜び
生成AIをDIYするのは、簡単ではありません。
-
ゼロから作るのは非現実的だが、ファインチューニングなら趣味レベルでも可能
-
GPU環境はクラウドで借りられるので、誰でも挑戦できる
-
データ集めや学習過程には落とし穴が多いが、それも含めて“育てる楽しさ”がある
要するに、自作AIは「効率のため」ではなく「楽しさと学びのため」にやるものです。
もし少しでも興味があるなら、小さな一歩から始めてみてください。
自分だけのAIが応えてくれる瞬間は、何ものにも代えがたい感動があります。
AIをただ“使う”だけじゃなく、“作る”楽しさを味わえる時代が来ているんです。
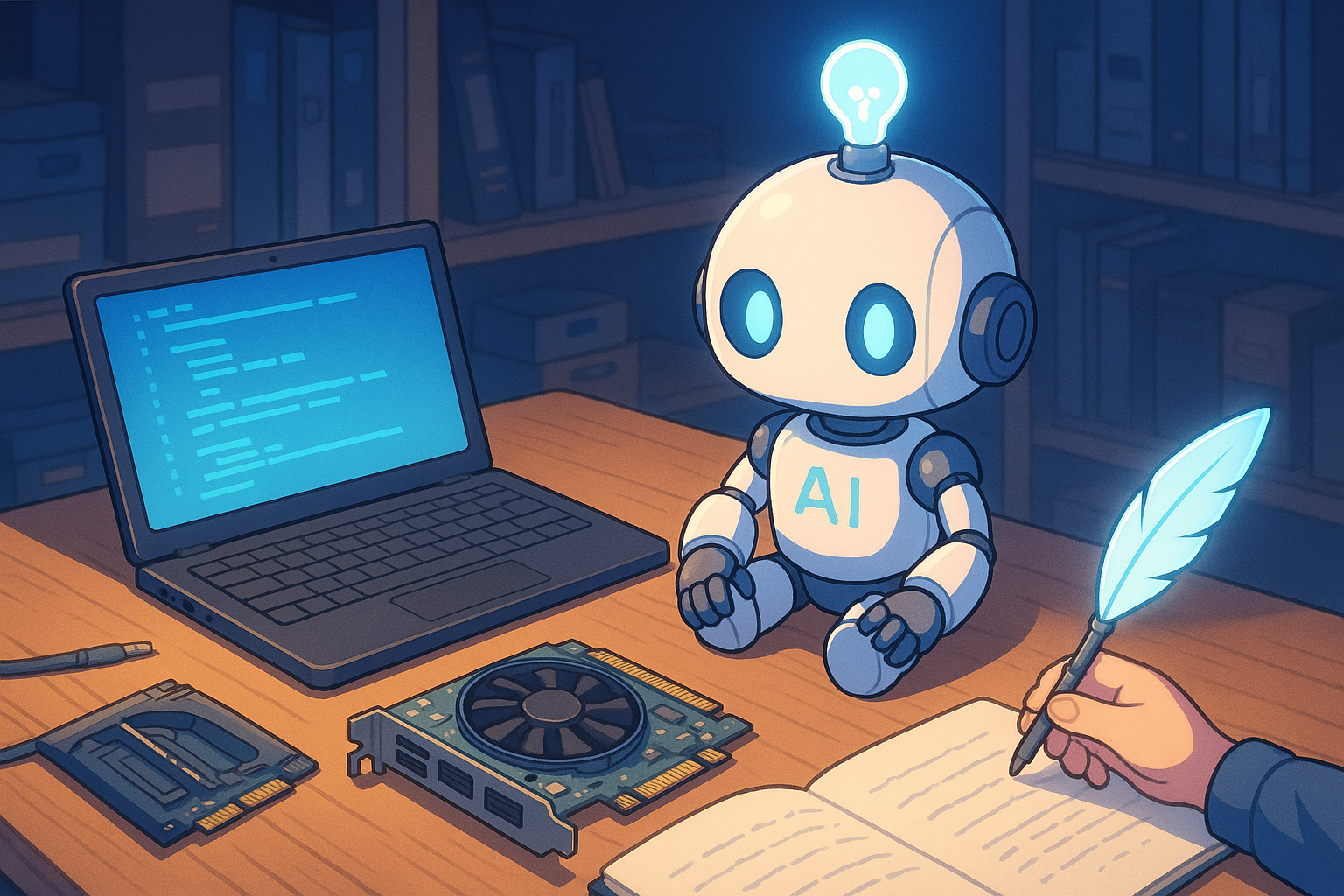
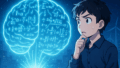

コメント