「また誤字脱字をやらかした……」
文章を書く人なら、一度や二度じゃなく何度も味わったことがあるはずです。
私もメールを送ったあとに気づいて冷や汗をかいたり、ブログを公開してから「うわ、打ち間違えてる」と頭を抱えたり。
でも最近は、その心配をかなり減らせるようになりました。
そう、生成AIによる文章校正のおかげです。
ただしAIができるのは、単なる誤字脱字チェックにとどまりません。
文章をもっと「魅せる」形に磨き上げてくれるんです。
今日はその秘密と実際の使い方、そしてまだ残っている課題について語ってみたいと思います。
単なる誤字脱字チェックの時代は終わった
昔の校正ツールといえば、誤字や脱字を赤くマークして教えてくれる程度でした。
Microsoft Wordのスペルチェックなんかが典型ですね。
もちろんあれはあれで助かりました。
でも「てにをは」の不自然さや、同じ言葉を繰り返してしまうクセなんかは見逃されがち。
ところが生成AIは違います。
文脈を理解し、流れを整え、場合によってはより自然な表現にリライトまでしてくれるんです。
例えば「この本はとても良かったです」と書いたとします。
AIにかけると「この本は心を揺さぶられるほど素晴らしかったです」と提案してくれる。
同じ「良い」でも、印象の強さが全然違いますよね。
つまりAIは「正す」だけでなく「魅せる」方向に文章を引き上げてくれるんです。
実際に役立つツールたち
具体的なサービスもいくつか紹介しましょう。
まずは有名な Grammarly。英語向けですが、誤字脱字だけでなく文体やトーンまで整えてくれます。
英語でメールを書くときに一度通すだけで、ぐっとプロっぽくなる。
日本語なら Shodo や 文賢 といった校正支援ツールがあります。
特にShodoは、文章を投げると読みやすさや感情表現の強弱まで分析してくれるので「なんか硬すぎるな」と気づけるんです。
さらにChatGPTやClaudeを使って「もっと柔らかくして」とか「感情を強めて」とお願いすると、校正を超えた「リライト」にも対応してくれる。
実際、私はブログを書くときに下書きをAIにチェックさせています。
すると「あ、ここちょっと回りくどいな」とか「同じ言葉を繰り返してるな」と、見逃していたポイントを突かれる。
人間の相棒というより、ちょっと厳しい編集者が隣にいる感覚です。
AI校正の面白い体験談
ここで少し脱線。
あるとき「今日は疲れた」とだけ書いた日記をAIに通したことがあります。
すると返ってきたのは「今日は心身ともに疲れを感じた一日だった」――いや、たった一文が急に文学的(笑)。
別の日には「ラーメンを食べた、美味しかった」と書いたら、「熱々のスープが体に染み渡り、一口ごとに幸福感が広がった」と変換されました。
もう小説かよ!って突っ込みたくなりました。
でもこの「過剰なくらい盛ってくれる」おかげで、自分の文章が平板になっていることに気づけるんです。
そこから「じゃあ自分ならどう表現するか」と考えるのが、意外と勉強になる。
AIはただの自動修正マシンじゃなく、発想を刺激してくれる存在でもあるんですよね。
残された課題
とはいえ、AI校正にも課題はあります。
一つは ニュアンスの潰れ。
人間があえて短く、そっけなく書いた文章を「もっと丁寧に」と直してしまうことがあるんです。
例えば「やばい、嬉しい!」というラフな表現を、AIは「非常に喜ばしいことです」と修正してしまう。
……いや、そうじゃない!と言いたくなる瞬間があるんです。
もう一つは 文責の所在。
AIの提案をそのまま採用したとき、それは「自分の言葉」と言えるのか。
文章は個性の表れでもあるので、「全部AIに整えられたら自分らしさが消えるんじゃないか」と不安になる人もいます。
だから私は「AIの提案はあくまで参考に、自分で最終判断を下す」ようにしています。
AIに頼りすぎない。これが今のところの正解でしょう。
未来の校正体験
これからのAI校正は、もっと進化するはずです。
たとえば「この文章をSNS向けに」「これは学術論文風に」と、用途ごとに最適化してくれる。
あるいは「この人に送るメールだから、相手の性格に合わせて柔らかく」とパーソナライズされるかもしれません。
さらに面白いのは「読み手の感情を推測して校正する」という未来像。
「この文章だと相手が怒るかも」と警告してくれるようになったら……ちょっと怖いけど助かりますよね。
私は将来、メールを書く前にAIが「今日は疲れてるでしょ?文章が尖ってるよ」と声をかけてくれる時代が来るんじゃないかと思っています。
もはや校正ではなく、人生の相談役(笑)。
まとめ
生成AIによる文章校正は、誤字脱字チェックを超えて「文章を魅せる」段階に入っています。
自然で読みやすく、感情を伝えやすい形に整えてくれる。
それは単なる修正ではなく、書き手の表現力を引き上げるサポートでもあります。
もちろんニュアンスの潰れや「自分らしさが失われる」リスクは残っています。
でも、AIを参考にしつつ最終判断は自分が下す。
そのスタンスさえ忘れなければ、AIは最高の校正パートナーになるはずです。
誤字脱字に怯えていた時代から、文章をどう「魅せるか」を考える時代へ。
文章を書く楽しみは、AIによってますます広がっていきます。
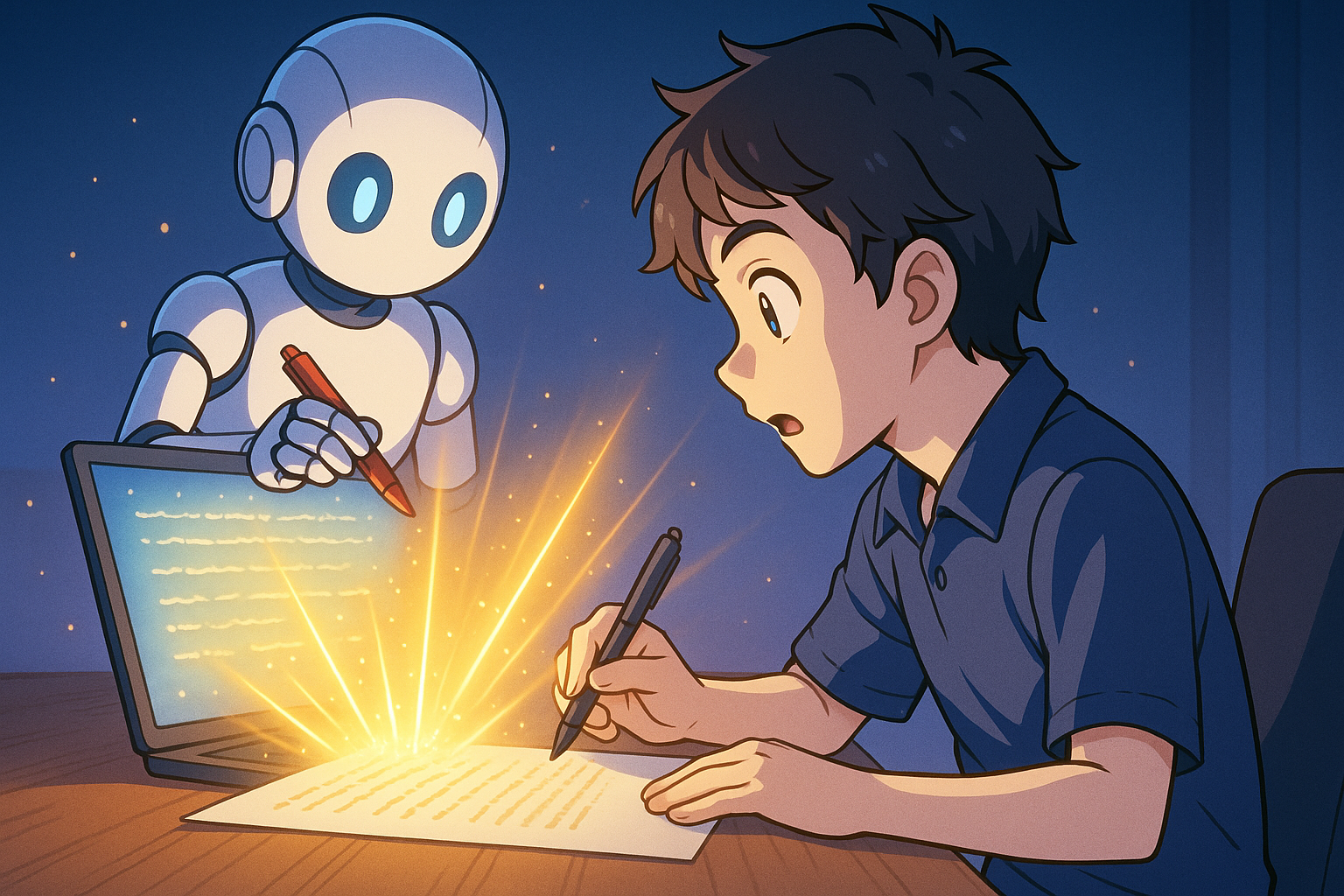

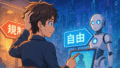
コメント