大学のキャンパスにも、生成AIの波が押し寄せています。
私はつい先日、後輩から「レポートをAIに手伝わせてもいいんですかね?」と真顔で相談されました。
そのとき私は、少しドキッとしました。だって、大学は「自分の頭で考える場」というイメージが強かったからです。
けれど現実には、生成AIはすでに学生生活の一部になりつつあります。
光と影。
この言葉がぴったりだと感じるのは、便利さの裏にあるリスクをどう捉えるか次第で、大学の姿がガラッと変わってしまうからです。
レポート作成に潜む甘い誘惑
生成AIの最も身近な使い方といえば、やっぱりレポート作成。
実は、仮にレポート書いてもらうとどうなるかな?と思って、「構成案」をAIに考えてもらったことがあります。
大学時代のレポート課題を思い出して、AIに「このテーマでレポートの流れを出して」と頼んだんです。
返ってきた答えは驚くほど整理されていて、「あ、これ大学時代にあったらそのまま提出してるかも」と思いました。
サークルの先輩から昔のレポートをもらってパクるとか、そういうのが私の時代の大学生あるあるだったと思うんですが、今はAIが“頼れる先輩”なんでしょうね。
でも「これって自分の力なのか?」という葛藤はありそうですよね。
まあ、それは別に先輩のレポート写しても同じなんですけど(笑)。
AIは甘い誘惑を差し出します。便利であるほど、「考える力」を手放しそうになる。
今の大学生は、この誘惑と戦っているのかと思うと、それはそれで大変だなあ、と思います。
教員が直面する新しい課題
学生がAIを使うなら、教員側も黙ってはいられません。
私の知り合いの教授は、「学生がAIで書いた文章をそのまま提出していないか、見抜くのが難しい」と嘆いていました。
文章がやたら流暢で、でもどこか中身が薄い。
「これ、本当に本人が書いたのか?」と疑い始めたら、もうキリがないそうです。
そこで大学によっては、「AI使用を申告するルール」を設けたり、「AI検出ツール」を導入したりと試行錯誤が始まっています。
ただ、AIも進化が速く、検出ツールをすり抜けてしまうこともある。まるでいたちごっこのようです。
この状況を見ていると、単に禁止するのではなく「どう使わせるか」を教育することの方が重要なんだろうなと感じます。
研究現場に広がる可能性
一方で、研究の場における生成AIの活用はワクワクします。
例えば論文の下調べ。以前は数日かかっていた文献調査が、AIを使えば一瞬で要約が手に入る。
もちろん正確性の確認は必要ですが、リサーチのスピードが段違いに上がります。
私は大学時代に哲学を学んでいたので、AIに「近代哲学の主要テーマをまとめて」と依頼したことがあります。
出てきた内容はざっくりしていたけれど、参考文献を深掘りするきっかけになりました。
「AIが入口を作り、人間が奥に進む」――そんな役割分担が研究の形を変えつつあるのかもしれません。
ただしここにも落とし穴があります。AIの答えをそのまま信じてしまうと、誤情報に足をすくわれる。
研究の精度を保つためには、AIに頼るほど「疑う力」が必要になるんです。
学生生活を彩るもう一つの顔
AIは学業だけでなく、学生生活の“裏側”にも入り込んでいます。
例えば、就活エントリーシートの添削。AIに見てもらうと、表現が一気に整うんですよね。
私の友人は「AIのおかげで志望動機がうまくまとまった」と笑っていました。
また、サークル活動でもAIが役立ちます。チラシのデザインをAIに頼んだら、プロ顔負けのポスターが完成。
今までのパワポで頑張っていたポスター作製が一瞬で終わるわけです。
大学のサークルのポスターなんだから、素人臭い手作り感があった方が逆にいい気もしますけど(笑)。
こうした小さな便利さが、学生生活をもっと軽やかに、楽しくしているのも事実です。
私が感じた不安と期待
ここまで書いてきて、正直な気持ちを打ち明けます。
私はAIを使った瞬間の「うわ、便利!」という高揚感も知っているし、その後の「これでいいのか?」という不安も知っています。
そしてその揺れ動く感情こそ、AI時代に大学が直面している本質だと思うんです。
人間が手放してはいけないのは「考える力」。
でもAIを排除するのではなく、むしろ「どう付き合うか」を学べるのが大学という場所なのかもしれません。
生成AIは光であり、影でもある。
けれど、光と影のコントラストが強いほど、未来は鮮明に浮かび上がってくる――私はそう信じています。
まとめ
生成AIが大学にもたらすものは、
-
レポートや研究での効率化という光
-
学生や教員が直面する倫理的・教育的な課題という影
-
学生生活の小さな便利さという彩り
この三つが入り混じった“キャンパスの新しい日常”です。
大学は知を育む場。だからこそAIを排除するのではなく、「どう共存するか」を考える舞台になるはずです。
未来の大学では、AIが当たり前に存在し、学生も教員もその光と影を抱えながら歩んでいく。
その姿を想像すると、不安よりもむしろワクワクする気持ちの方が大きいのです。

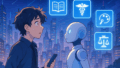

コメント