「AIって本当に考えてるの?」
これは、私が最初にChatGPTを触ったときに頭に浮かんだ素朴な疑問です。
まるで人間と会話しているように自然な返答が返ってくる。だけど頭の片隅では「いやいや、これはただの計算なんだよな」とも思う。
じゃあその“計算”って、いったいどういうものなんでしょうか?
今回は、生成AIを支えている計算の舞台裏を、できるだけわかりやすく、そしてちょっと感情を交えながら解き明かしていきます。
脳のようで脳じゃない「ニューラルネットワーク」
生成AIの仕組みを語るうえで欠かせないのが、ニューラルネットワーク。
名前だけ聞くと「人間の脳そのもの?」と想像しがちですが、実際には脳のニューロンをヒントにした“数式のネットワーク”にすぎません。
例えば、「カレーを作りたい」と言われたら、AIは“じゃがいも・にんじん・玉ねぎ”を候補に挙げ、それぞれの登場確率を計算して、最も自然な組み合わせを選ぶ。
この確率の積み重ねが、あたかも“意味”を理解しているように見える。
私は初めてこの仕組みを知ったとき、正直ちょっとがっかりしました。
「え、意味なんて理解してないのかよ!」と(笑)。
でも同時に、「それでも人間と自然に会話できるレベルまで来ているのって、逆にすごくないか?」とも思ったんです。
理解していないのに理解しているように振る舞える――ここにAIの魔法があるんだと気づきました。
GPUが担う「筋肉のような計算力」
AIが言葉を操れるのは、とんでもない量の計算をこなしているからです。
その主役がGPU。もともとはゲームの映像処理用に開発されたものですが、並列計算が得意という特性からAIの学習に引っ張り出されました。
イメージとしては、人間の脳がしている細かい仕事を、何千人もの作業員に分担させている感じ。
だからAIは、一瞬で大量の「次に来る言葉の確率」を計算できるのです。
私は以前グラフィックボードを買い替えたことがあります。
もちろん、ゲーム用に。
それで、試しにローカルAIモデルを動かしたら「ファンが爆音で回り出す」→「部屋がサウナ化」→「夏場だったので熱中症になりかける」という三段落ち(笑)。
そのとき、「AIの“賢さ”は膨大な計算の上にあるんだ」と身をもって理解しました。
計算の裏にある「重み」と「パラメータ」
もう少し突っ込むと、AIの思考は「パラメータ」という膨大な数字の集まりでできています。
ChatGPTのような大規模モデルだと、その数は数千億。
一つひとつのパラメータが「この単語とこの単語はどのくらい関連しているか」を表していて、入力されるたびにその重み付けをもとに計算を走らせます。
これを聞いたとき、私は「人間の“経験”って、もしかしてこういう重みの集積に似ているのかも」と感じました。
失恋した経験がある人は恋愛小説を読むと涙が出やすい。旅好きな人は風景描写に敏感に反応する。
そんな“個人の重み”が、私たちの思考を形作っているんじゃないかと。
もちろんAIは本当に感情を持っているわけではありません。
でも、仕組みを知ると「人間の思考とAIの計算って、案外遠くないのかも」と妙な親近感が湧くんです。
AIは夢を見るのか?
ちょっと飛躍した考えかもですが、AIが文章を生成している姿を見ていると、「こいつ夢でも見てるのかな」と思うことがあります。
大量の確率の中から最もらしい単語を選び、物語を紡ぐ。
それって、人間が眠っているときに記憶の断片をつなぎ合わせて夢を作っているのと似ていませんか?
もちろん科学的には違います。でも、そんな風にAIの“思考”を夢に重ねると、なんだか愛おしくなるんです。
生成AIを彼氏や彼女にしてる人がいる、というも納得かな、と。
怖くもありますけどね。
限界もまた「計算」から来ている
AIの答えがときどきズレるのも、この計算の仕組みの限界から来ています。
-
文脈を広く見すぎて要点を外す
-
自信満々に間違う(いわゆるハルシネーション)
-
長期的な因果関係を追えない
私もAIに歴史的な出来事を聞いたとき、「そんな人物いなかったよな?」という答えが返ってきて、慌てて調べ直したことがあります。
まるでテストで堂々と間違った答えを書いて減点される自分を見ているようで、ちょっと親近感を覚えました。
AIは「考える」のではなく、「計算している」。
だからこそ、その強さと弱さを理解したうえで使うことが大事なんです。
AIに計算を任せすぎた結果
実は一度、私はAIに計算を完全に丸投げして痛い目を見たことがあります。
ブログのアクセス解析をAIにやらせたのですが、結果はもっともらしいのに全然違う。
それを鵜呑みにして記事を修正したら、アクセス数が逆に落ちてしまいました。
あのとき、「AIはあくまで補助。最後に考えるのは自分」という原則を忘れていたんです。
便利さに頼りすぎると、自分の頭がどんどん鈍ってしまう――そんな教訓になりました。
まとめ:AIは「考えるふりが上手い計算機」
生成AIの計算の秘密をまとめると、
-
ニューラルネットワークが確率計算で次の単語を予測している
-
GPUの圧倒的な並列計算力がそれを支えている
-
膨大なパラメータが「経験のようなもの」を作っている
-
だから人間の思考に似た錯覚を与える
-
でも限界もあり、最後の判断は人間に委ねられている
AIは「考えている」わけじゃない。
でも、計算の積み重ねが“考えているように見せる”のです。
私はこの正体を知れば知るほど、「AIってやっぱり面白いな」と思うようになりました。
そして同時に、「最後に考えるのは自分」という当たり前の事実が、より強く胸に刻まれたのです。
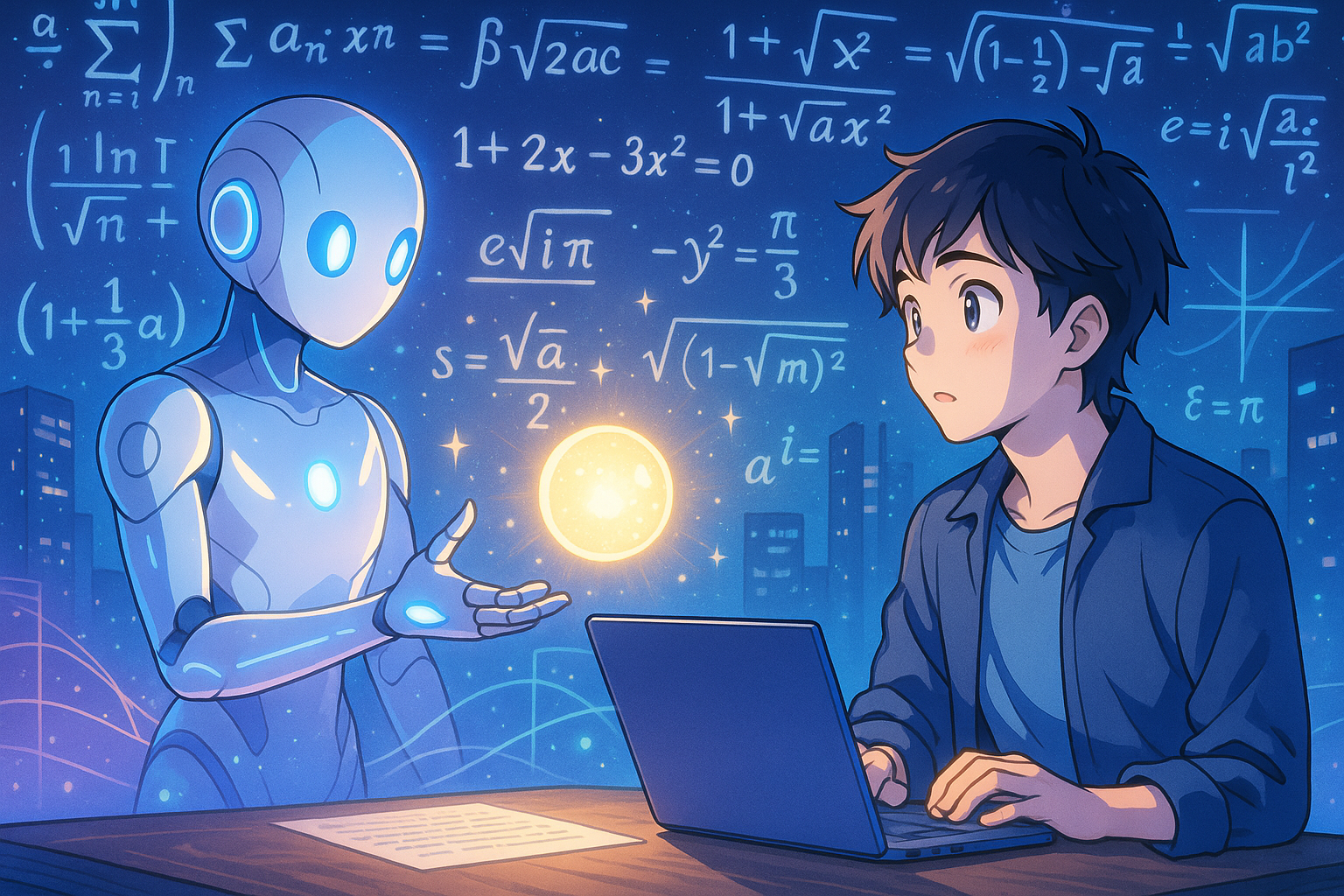


コメント